當(dang)社は1989年から日本國と研修(xiu)(xiu)生事業を協力(li)し始めて、1992年に中(zhong)日研修(xiu)(xiu)協力(li)機(ji)構(gou)のメンバーになり、中(zhong)日研修(xiu)(xiu)協力(li)機(ji)構(gou)の25社理事機(ji)構(gou)の一つにもなっています。日本國際研修(xiu)(xiu)協力(li)機(ji)構(gou)(JITCO)が作成した中(zhong)國送り出し機(ji)関の順位表では、當(dang)社の順位が上位にあります。
當社は主に日本政府(fu)に許可された業界へ技(ji)(ji)能(neng)(neng)実習生(sheng)と技(ji)(ji)術スタッフを派遣しています。既(ji)に30あまりの都道(dao)府(fu)県へコンピューター技(ji)(ji)術スタッフ、コック、電気機(ji)械(xie)エンジニアなど専(zhuan)門技(ji)(ji)術のある人材(cai)と裁縫、布(bu)織り、水産加(jia)(jia)工(gong)(gong)、食品加(jia)(jia)工(gong)(gong)、機(ji)械(xie)加(jia)(jia)工(gong)(gong)、金屬加(jia)(jia)工(gong)(gong)、板(ban)金、建築、印刷(shua)、製(zhi)本、熔接、電子組(zu)み立て、機(ji)械(xie)、家具製(zhi)作、メッキ、プラスチック成型、塗裝、工(gong)(gong)業包裝、石(shi)材(cai)加(jia)(jia)工(gong)(gong)などの職種に従事する実習生(sheng)を送り出(chu)しました。毎年(nian)日本へ延べ2000人ぐらいの技(ji)(ji)能(neng)(neng)実習生(sheng)を派遣しています。
30數年の技(ji)能実(shi)習生の派遣の歴史を振り返(fan)って見れば、忠誠と勤勉(mian)で、規律をよく守り、苦労に耐(nai)え我慢強(qiang)いのが煙臺技(ji)能実(shi)習生の特(te)徴です。これらの特(te)徴で、受(shou)け入れ企業(ye)と組合より好評を博してもらいました。當社はきびしく、基準通りに候(hou)補者(zhe)を選び出し、そして、事前教育と出國後の管理も徹底して取り組んでいますので、受(shou)け入れ企業(ye)と日本、中國の関係機構(gou)より高い評価を受(shou)けており、同時に、実(shi)習生本人(ren)および両親にも満足してもらっております。
當社が送り出している技能実習生には次の特徴があります。
① 受入企業の経営、管理、人および周辺環境が比較的よいことである。
當(dang)社(she)(she)の実習生を初めて受入れる企(qi)業(ye)(ye)に対(dui)して、実習生が日本へ赴く前に、擔當(dang)者を日本へ行(xing)かせて、仕事や生活條件および周(zhou)辺環境について確認しています。明らかに問題(ti)があって、なおかつ改善できない企(qi)業(ye)(ye)に対(dui)しては、派遣しないことにしています。
いままで當(dang)社(she)(she)と提(ti)攜してきた企(qi)業(ye)(ye)は倒産(chan)することがないようです。
② 人間味(wei)のある管理を実行すること。
當社は日常管理(li)のほかに、次の措置を取って管理(li)を強(qiang)めます。
一つは駐日(ri)(ri)本(ben)(ben)(ben)國事務所が協力(li)することです。當社(she)はいま日(ri)(ri)本(ben)(ben)(ben)では日(ri)(ri)本(ben)(ben)(ben)支社(she)の他(ta)、東京、大阪、名古屋、福岡、鹿児島、広島、北海道、仙(xian)臺、金沢などの十ヶ所で駐日(ri)(ri)本(ben)(ben)(ben)國事務所を設(she)置しております。地域によって、在日(ri)(ri)の6000名以上の実習生の管(guan)理を実施しております。そして、日(ri)(ri)本(ben)(ben)(ben)の受入機関(guan)が実習生を連絡(luo)、管(guan)理、調和することに協力(li)します。
二(er)つ目は実(shi)習(xi)(xi)生(sheng)(sheng)を定期(qi)的(de)に激勵に行くことです。一般的(de)に當(dang)社の幹部、あるいは業務擔當(dang)者(zhe)が毎(mei)年少なくとも2回ほど受け入れ企(qi)業も訪問して、アドバイスを聞いたり、実(shi)習(xi)(xi)生(sheng)(sheng)を激勵しています。実(shi)習(xi)(xi)生(sheng)(sheng)達の思(si)想問題を説得して解(jie)決しながら、実(shi)習(xi)(xi)生(sheng)(sheng)からの意見を聞いたり、実(shi)習(xi)(xi)生(sheng)(sheng)と企(qi)業の関係を改善したりしています。
三つ目は実(shi)(shi)習生(sheng)リーダーを派遣することです。日本語が分かる、管理ができる社員(yuan)を受入機関或(huo)いは企業へ派遣して実(shi)(shi)習生(sheng)管理の協力をすることです。実(shi)(shi)踐では、効果が大(da)変(bian)よいです。


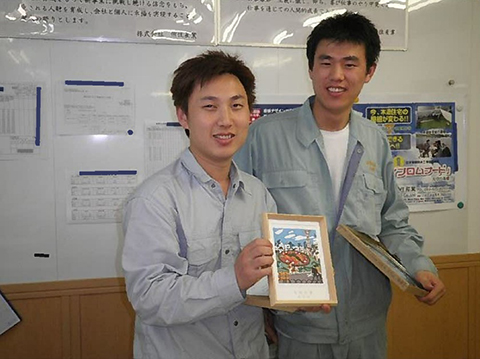


日本の受入機関、受入企業と実習生業務を提攜することを心より歓迎しております。
志をもっている方が、當社或いは関連人材センターに応募することが心より歓迎しております。
外國で実習することは、家庭の経済狀況を変えられるばかりでなく、実習生の將來をも変えます。
外國で実習することは、より一層の素晴らしい人生を作り上げます。
一人の出國で、家族も受益。
三年の実習で、一(yi)生の受益。